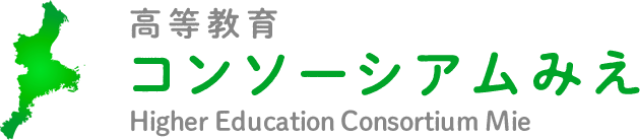2022年度県内高等教育機関合同開講授業「食と観光実践」(後期集中講義)で事後学習回(最終発表会)が実施されました
-
南伊勢町、度会町、玉城町をフィールドとして、「食と観光」の“体験“を切り口に、地域課題の発見とその解決方法をグループワークから学んでいきます。
今年度のテーマは「3町(南伊勢町、度会町、玉城町)での食と観光にまつわる体験プログラムを!-サニーロードを軸としてつないだ体験・学びの旅の提案-」で、三重短期大学5名、皇學館大学3人、四日市大学5人、鈴鹿大学2人、三重大学10名の全25名の学生が参加しました(留学生含)。
●10月23日(日)フィールドワーク①はこちら
●11月6日(日)グループワークはこちら
●11月27日(日)フィールドワーク②はこちら
12月25日(日) 事後学習回(最終発表会:三重大学)
事後学習回(最終発表会)の様子をご紹介します。
・開会のあいさつ、本日の流れ
皇學館大学 教育開発センター 池山 敦准教授
・発表、質疑応答
・講評 一般社団法人松阪市観光協会 山本 真帆氏
射和文庫 竹川 裕久氏
・総評 四日市大学 総合政策学部 小林 慶太郎教授
・閉会のあいさつ 鈴鹿大学 国際地域学部 冨本 真理子教授
【司会進行】 三重大学 人文学部4年 李睿琪さん
【各班の発表に対する感想・質疑応答】
玉城町
4班「デートコースの提案」
- 大学生のみならず、30代、40代にもヒットしそうな内容でした。実現できそうな提案でとても参考になります。歩いて散策することで玉城町をより知るきっかけとなると思います。どの位の距離感、コース等地図でみせてもらえると分かりやすいと思いました。(松阪市観光協会 山本氏)
-
レンタルサイクルで玉城町を周るというプランですが、公共交通機関を使わないとなかなかいけない場所です。アクセスはどのように考えていますか。(学生)
→JRや三重交通と期間限定(夏休み、週末等)でコラボできるように行政から働きかけてほしいです。
 (写真)開会のあいさつ |
 (写真)プレゼンの様子 |
6班「世界に一つだけの新聞を作ろう」
-
わたし新聞を作ろうと考えた背景をもう少し聞きたいです。(学生)
→玉城町を初めて訪問し、村山龍平氏の偉業(社会貢献活動)を初めて知りました。語り部の方、記念館でさらに学びました。若者の新聞離れが目立ちますが、錯綜するネット世論と距離を置き、責任を持って持論を展開できる事が役割だと思います。新聞の多面性をもっと若者に知ってもらうために“わたし新聞”を作りたいと考えました。
 (写真)プレゼンに聞き入る先生方 |
 (写真)みなで助け合う様子 |
度会町
1班「Let Us Go WATARAI」
-
ジビエ肉は具体的にどのようなルートで購入するのか、既に購入可能な場があるのか詳細を教えてください。(松阪市観光協会 山本氏)
→まだ調べ切れていません。 - お茶は差別化が難しいです。外宮の歴史とお茶、熊野古道と宮川のつながりを深堀しても良かったのではないでしょうか。(射和文庫 竹川氏)
その他、データ参照の年月記載を行うこと、スライド9枚目川霧とお茶のおいしさについて調べなおすようにと指摘されていました。
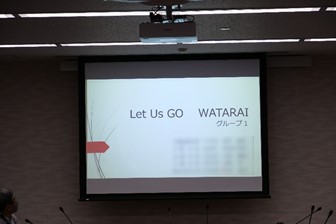 (写真)プレゼンの様子 |
 (写真)役割分担し、みなで発表する様子 |
5班「いつもと違う場所 行ってみませんか」
- 地域資源が少ない地域でよく考えられたと思います。自然満喫型ですが、背景として「外宮の歴史とお茶の歴史」:縦糸と横糸をつなぎ合わせる考え方をされてみるとまた違った視点が見えてくるかもしれません。(射和文庫 竹川氏)
- 県の市町村別観光客数、国の動向:観光白書から背景を掘り起こしテーマを設定している点が良かったです。(三重大学 学生総合支援機構 志垣 智子特任講師)
 (写真)プレゼンの様子 |
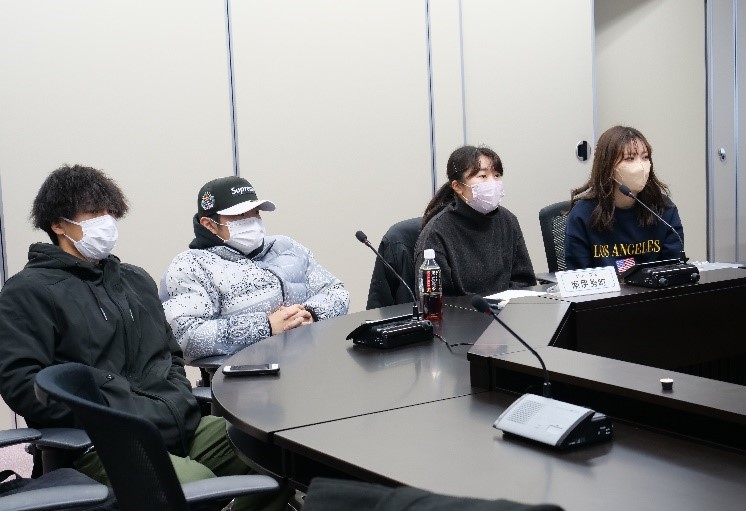 (写真)聞き入る学生の様子 |
南伊勢町
2班「南伊勢でスマホ捨ててみた」
- 空き家バンクに登録している1棟を宿泊施設にという提案ですが、実際知らない人同士が一軒家に宿泊するのはハードルが高いと思います。友達同士で楽しむコースを再考してもよいのではないでしょうか。(松阪市観光協会 山本氏)
- 実際、スマホを捨てて行きますか?(首を振る学生)、なのでもうひと工夫が必要ですね。(四日市大学 小林教授)
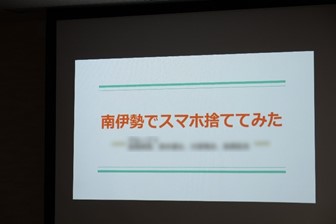 (写真)プレゼンの様子 |
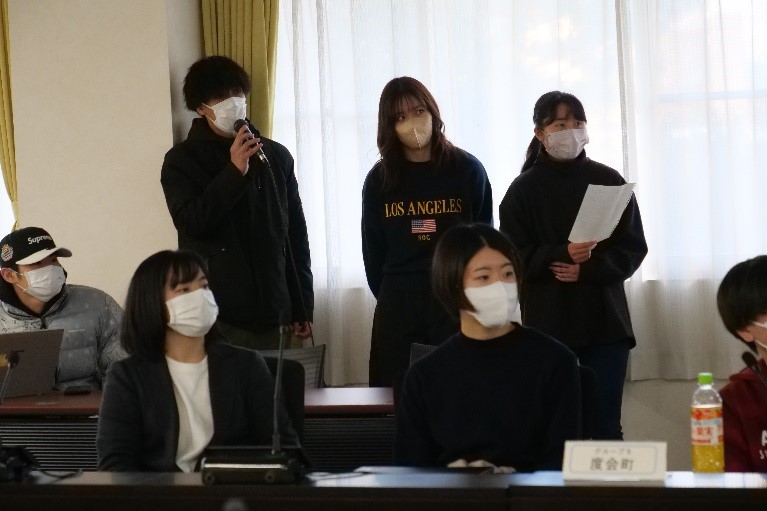 (写真)互いに協力する様子 |
3班「Welcome to our Minamiise」
- 6年間本講義を担当してきて、初めて動画を作ってきたグループがいて楽しく鑑賞しました。時代を感じましたし新鮮でした。(四日市大学 小林教授)
- 通訳を大学生に依頼することもよいですが、「#やさしい日本語」が流行っていて、住民と普段通り会話することを目的としている外国人もいます。そのようなターゲット層を考えてもよいのではないでしょうか。(鈴鹿大学 冨本教授)
- 旅行者との交流の中でみかんを種から植えて、成長段階を旅行者と共有したらよいのではないでしょうか。リピーターにつなげたい、が本音ですが過程を行政がブログやソーシャルで発信し、数年後の来訪を狙うのも良いと思いました。(学生)
 (写真)PCを操作する学生 |
 (写真)動画を披露する様子 |
 (写真)全体の様子1 |
 (写真)全体の様子2 |
【講評者の方々の感想】
- 観光資源が乏しい地域にもかかわらず皆さんの努力のあとがみられ、感心して聞かせて頂きました。(射和文庫 竹川氏)
- どのプランも実現可能性が高いと感じました。また刺激的でワクワクする時間でした。皆様、年々パワーアップしているように感じます。学生の皆様と関わらせていただけたこと、感謝いたします。(松阪市観光協会 山本氏)
【学生の感想】
- 最終発表が無事終わり、ホッとしています。プレゼンの導入はかなり悩んだので評価していただき嬉しいです。この講義を受けて大変だと思う部分はありましたが、先生の様々なお力添えのお陰で、最後まで楽しく頑張れたと感じています。本当にありがとうございました。また、観光プランを考えるためにはこんなにも多角的に考えなければいけないのかと、とても勉強になりました。私とは違った視点で発表している他の班の発表を聞くのが面白かったです。新しい経験がたくさんできました。この講義に参加して良かったと思います。(三重大学・生物資源学部、度会町担当5班)